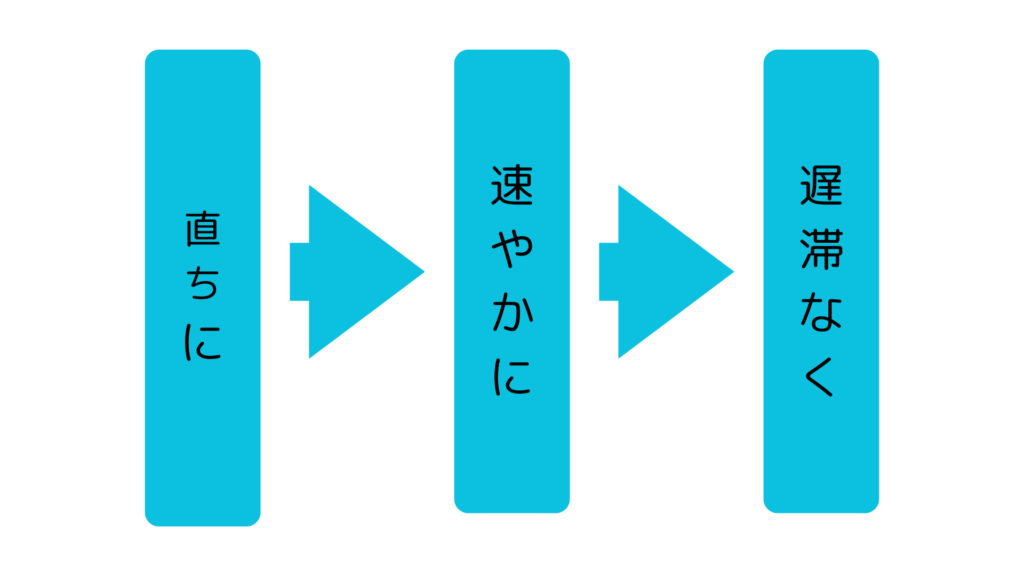法律用語や契約用語は難しい言葉がたくさん出てきます。
文章の構成や接続語の使い方など本当に複雑だと思います。
そんな難しい専門用語をできるだけわかりやすく説明します。
期間とは、ある時点からある時点までの時間的間隔のこと
期間の使い方の具体例として、有効期間があげられます。
「1月1日から12月31日まで有効とする」このようなものが期間の使い方の具体例です。
また、「相続の開始があったことを知ったときから3カ月」、というように、日、週、月、年単位よって定めることも可能です。
期日とは、ある行為をなすべき、あるいは法律効果が発生する特定の日のこと
契約上の話でいえば、「支払日」「引渡日」などが該当します。
使い方のポイントは、「支払期日は令和5年4月1日とする」というように具体的に決めることです。
この定めがあいまいだと、トラブルの原因となりますので注意が必要です。
時期とは、期日よりさらに狭く、特定の時点を指すもの
例えば、「4月1日午後1時に御社にお持ちして引渡します」というように、期日よりさらに時点特定して使います。
期限とは、法律効果の発生、消滅を将来発生することが確実な事実によらせる場合の、その事実の発生のこと
「期間」「期日」「時期」が時間や時点を指すことに対して、「期限」はある事実の発生を指しているという点において違いがあります。
ただ、将来発生することが確実な事実の典型例は一定の期日の到来であるので、結果「期限」は一定の時点を指すことが多くなります。
契約書でよく使われるのが「有効期限」で、終期を定めることで、法律効果の消滅を一定の期日の到来にかからせるときに使われています。
間違った使い方の例として「有効期間」と「有効期限」があります。
「有効期限は1月1日から12月31日までとする」は誤った使い方です。
「期限」は一定の時点の到来ですので、正しい使い方は「有効期限は12月31日とする」が正しい使い方になります。
「期間」「期日」「時期」「期限」は、時間を表す言葉としてよく使われます。
特に「期間」と「期限」は混同しやすいので、使うときには少し言葉の意味を思い出していただけると、正しく使えると思います。
参考になったのなら幸いです。